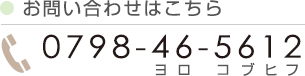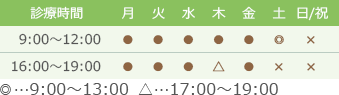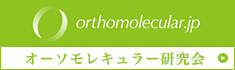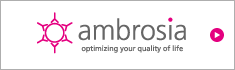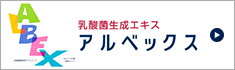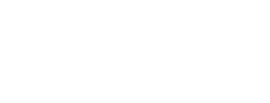栄養で身体が変わる
こんにちは、院長の栗木安弘です。
栄養療法を知るようになり、
サプリメントを飲み始めてから体の調子はすこぶるよくなりました。
もう7~8年前になりますが、サプリメントを飲み始める前は、
空腹時の胃の痛みが強く、今考えればピロリ感染があり、胃潰瘍か胃炎があったかと思われます。
元々尿酸値が低いガン家系なので、あのまま放置しておれば胃がんになっていた可能性は十分ありました。
またパンやご飯といった糖質やアルコールも多く、タバコも吸っていたこともあって、
歯のトラブルや汚れが目立つなど、よく歯科を受診していました。
ニキビ、粉瘤など皮膚トラブルもよく出来ていました。
「疲れた、疲れた」を連呼、二日酔い、頭痛、羞明、悪夢、扁桃腺腫大にも悩まされていました。
40歳で、タバコをやめて、糖質をできるだけ減らし、タンパク質を多めに摂取、
ピロリ除菌も行い、手のひらいっぱいのサプリメントを飲むようになってからというもの、
花粉症以外(これだけはなかなか)の症状はあまり気にならなくなりました。
栄養療法に出会っていなければ、いろんな不調や病気で悩まされ、薬ばかり飲んで、
肉体的・精神的ストレスを抱え、悶々とした勤務医生活を送っていたに違いありません。
栄養は心身だけでなく生き方まで変えてくれます。
来年もまた多くの方を栄養で変えて行きたいと思います。
医師が語る栄養学
こんにちは、院長の栗木安弘です。
昨日は、病気を治す立場の医師が「医師が語る栄養学」というタイトルで講演にされるというので心斎橋まで足を運びました。
講演内容としては、
5大栄養素について
各栄養素がどのような食材に含まれているのか
サプリメントの紹介など、一般向けのやさしい内容でしたが、
個人的には医師としてもう少し臨床に結びつけた内容がよかったなぁと感じました。
また医師としては、食事の見直しや食事で足りない部分をマルチサプリメントで補うという発想だけでなく、
各栄養素が生体にどのように作用するのか?
栄養素が疾患との関わり
血液検査の深読みによる栄養評価
栄養の消化吸収・代謝
という部分を理解し、テーラーメイドな分子栄養アプローチをすべきだと思いました。
がんと栄養療法(
こんにちは、院長の栗木安弘です。
ある意味、栄養療法の目的はがんの予防、再発防止、治療ではないかと思っています。
今年も多くの芸能人ががんになって治療を受けておられましたが、
毎年検診を受けていたにもかかわらずがんを発症したり、
手術しても再発を繰り返したり、手遅れの状態であったり、
術後の後遺症や抗がん剤の副作用で苦しんでいる方もおられるようでした。
私自身がんになったことはありませんが、
もしなった場合には、標準治療を受ける受けないに関わらず、栄養療法は続けます。
世間では、早期発見早期治療が謳われていますが、
できるだけ抗酸化対策、腸内環境改善をおこなうことでがんを予防したいと思っています。
以前のブログでも述べましたが、
がんは糖尿病や高血圧のように慢性疾患であると栄養セミナーで教えていただきました。
「がんと闘うな」ということで最近では放置されるケースもありますが、
早期でも末期でも、出来るだけがんに打ち勝つの栄養状態(タンパク質と貧血の改善)と免疫状態ををよくすることで、
治療による副作用の軽減や、たとえ治療ができない場合でも共存できるかと思います。
パラダイムシフト
こんにちは、院長の栗木安弘です。
先日、京都で栄養と食とアンチエイジングのセミナーがありました。
講演内ではパラダイムシフトという言葉が出てきましたが、
パラダイムシフトとは、
ある時代・集団を支配する考え方が、非連続的・劇的に変化すること。
社会の規範や価値観が変わること。
パラダイムチェンジ。パラダイム変換。発想の転換。
つまり今までの常識が変わるという意味です。
医療の世界でも時々こうしたパラダイムシフトがあります。
最近では、
傷は消毒しなくてもいい
コレステロールは高い方が健康的
卵の制限はいらない
糖尿病はカロリー制限ではなく糖質制限(主食を減らす)
ケトン体は危険ではなく安全
など従来の常識が見直されているようです。
少し突っ込んだところでは、治療=薬、皮膚の治療=ぬり薬
という方程式も、そろそろ見直されてもよいかと個人的には思っています。
各論総論
こんにちは、院長の栗木安弘です。
先週土曜日は大阪で皮膚科地方会がありました。
多くの症例発表があり、私もフェリチンと鉄に関する発表をさせていただきました。
いつも学会に出席するたびに発表内容や質疑応答を聴くと、皮膚科だけでなく、学会全体がそうですが、
病理組織診断が正しいかどうか
手術などの治療内容の検討
薬(ぬり薬)をいかにうまく使うか
治療が適切であったかどうか
珍しい疾患
など病気や治療といった表にあるところばかりに注目されているなぁと思います。
その一方で、
病気がなぜ起こるのか?予防法
手術や治療の前の栄養管理
血液検査や基準値について
薬を減らす対策
食事と栄養と皮膚の関わり
などは臨床上は非常に重要なことにも関わらず、こうした発表や検討はあまりされないようです。
それが医学というものかもしれませんが、
各論(病気)だけではなく、もっと総論(病人)についても研究検討してほしいと願っています。
かゆみはつらい
こんにちは、院長の栗木安弘です。
かゆみは何の前触れもなく突然出てきますが、
多くは仕事中は少なく、帰宅して家でリラックスした時によく経験します。
また、食後やアルコール・カフェインなどを摂取した場合、入浴後にもよくあります。
当然何かの刺激物が付着した場合も生じますし、
体内の異常のあらわれとしても生じますが、多くは鉄不足や糖質過剰の方に認められます。
世間一般にはかゆみは、「掻かないこと」が正しい行為のような風潮で、
「掻くのはよくない、掻いたらダメ」と叱咤されている方、患者さんに指導されている皮膚科医も見受けられます。
そのためかゆみを我慢されている方もおられますが、
かゆみ自身もつらいけど、それを我慢する方がもっとつらいような気がします。
私自身も痒かったら掻いていますし、患者さんにも「我慢せず、掻けばよい」と指導しております。
掻いたら悪化する、バイ菌が入ると思われていますが皮膚が丈夫であればそんなことはありません。
それでも掻くのが嫌なら、かゆみ対策として、
冷やす
体を動かす
かゆみ止めを飲む
痛み刺激に変えて紛らわす。(痛みはある程度我慢はできる)
あたりです。
コレステロールや胃酸など本来体に必要な成分が病気の犯人として思われているように、
皮膚科においても“掻くこと”が皮膚が治りにくい原因や悪化因子として考えられていることにとても違和感を覚えます。
薬疹
こんにちは、院長の栗木安弘です。
昨晩の仰天ニュースはアレルギー特集で、
薬の副作用により全身の皮膚がただれてしまうステーブンス・ジョンソン症候群が紹介されていました。
こうした番組を観るとやはり薬って怖いなぁと改めて思います。
薬は体内での代謝・解毒・排出がうまくできなければ副作用も起こりやすく、
薬の代謝や解毒にはアルブミン、肝におけるチトクローム酵素、抱合などが関わっており、
こうした反応の背景にはタンパク質や鉄やグルタチオンやコンドロイチン硫酸といった栄養素が存在します。
つまり栄養障害がある方は薬の副作用があらわれやすいということです。
番組内では、胃薬(胃酸抑制剤)が原因薬剤だったと述べておられましたが、
多くの医師は胃薬って副作用も少なく軽いという認識しかなく、
胃痛以外に、ステロイドや痛み止め内服、薬剤が多い場合に安易に抱き合わせで処方されることがよくありますが、
番組内で紹介された薬疹をはじめ、長期内服により胃酸分泌が抑制され栄養障害を生じることがよくあります。
アトピーの原因
こんにちは、院長の栗木安弘です。
アトピーは、
角層内セラミド減少
真菌、黄色ブドウ球菌
フィラグリン遺伝子異常
神経系細胞
などが原因として報告されていますが(一体どれやねん)
実際はこうした研究成果が発表されてもすぐに治療薬として応用されることはないようです。
そのため現状はステロイド外用剤やスキンケアでのコントロールが主体となりますが、
日々皮膚の変化を診察し、血液検査を診ていると、
アトピーを含め、皮膚の変化は明らかに内臓の変化(栄養障害)であることはほぼ間違いないようです。
栄養障害の原因は、
食事のかたより(糖質過剰、ω6過剰、タンパク質不足)
消化吸収(ピロリ、胃酸分泌低下、リーキーガット、腸内環境)
肝機能障害(脂肪肝など)
貧血
需要亢進(成長、妊娠、スポーツ)
薬剤性
といった栄養の吸収・代謝・運搬障害が複雑に絡み合っているため、
どこに原因があってどの栄養素が優先的に必要かは個人個人違ってくるため、難しい反面やりがいもあります。
「今の医学ではほとんどの病気は治せません。コントロールするだけです。医学で治せるのは感染症の一部くらいです」
「アトピーも生活に支障のない程度にステロイドやスキンケアでコントロールすることです」
と某皮膚科教授がある雑誌で述べていましたが、これはある意味負けを認めているような印象を私は受けます。
アトピーコントロール、原因解明もよろしいが、早期に治療に結びつける対策がやはり必要です。
入れてもダメなら出してみる
こんにちは、院長の栗木安弘です。
不足した栄養素を至適量投与することが栄養療法の基本ですが、
今までの経験から、それでもよくならない患者さんもおられます。
とくに経過が長い疾患や、皮膚の炎症やジクジクがひどい方、色素沈着やゴワゴワ(苔癬化)が著明な方は、
重金属蓄積の影響が大いに疑われるため、
栄養を入れることよりもむしろ、こうした有害金属を出すことを優先する方がよいかと最近は思っています。
重金属には、鉛、水銀、カドミウム、ヒ素、アルミニウムなどがあり、
こうした重金属を排泄させるためのキレーションやデトックスが一部のクリニックで行われています。
金属の排泄はおもに点滴で行われますが、
鉄、亜鉛、αリポ酸、システインなどにも排泄するはたらきがあるため、優先的に経口投与したり、
肝臓の解毒機能をアップさせたり、便秘がひどい場合には、プロバイオティクスやプレバイオティクスのように腸内環境の改善なども併用することが必要となります。
栄養の吸収
こんにちは、院長の栗木安弘です。
栄養療法は食事の見直しやサプリメントを用いて不足した栄養素を補給していきますが、
やはり消化吸収が悪いと、いくらいい食べ物、良質なサプリメントを服用してもその効果は乏しいでしょう。
栄養療法が効く、効きにくい差も消化管にあるかと思われます。
とくに胃酸はが少ない方(日本人の約7割くらいが少ないと…)は、
ペプシンという消化酵素が作られにくくなりますので、タンパク質の消化が悪くなり、吸収しにくくなります。
さらにビタミンB12、亜鉛、鉄、カルシウム、マグネシウムの吸収も悪くなります。
また胃酸は、脂肪消化に必要なリパーゼの分泌に関与するため、脂肪の吸収も悪くなります。
そのため通常の脂溶性ビタミン(ビタミンAやEやD)を摂取しても、その効果は乏しいため、
サプリメントは脂肪を吸収しやすい形に乳化したミセルタイプのものをおすすめします。
ただしミセルタイプのサプリメントは、通常の保険のビタミン剤や市販サプリメントにはほとんどなく、
作り方も複雑になるため通常のサプリメントよりも高額となります。
栄養を入れることばかりではなく、消化吸収を良くしたり、ミセルタイプのサプリメントに変更するなど、
いかに吸収させるかも栄養療法がうまくいくかどうかのポイントです。