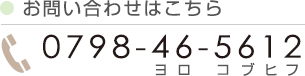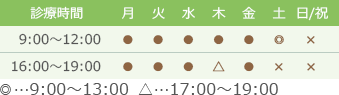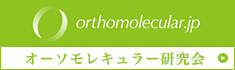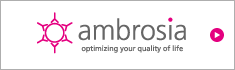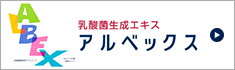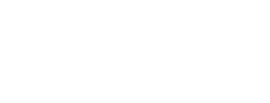皮膚掻痒症
こんにちは、院長の栗木安弘です。
皮膚に何も出来ていないのにかゆみが生じる疾患をいいます。
かゆみの原因は内臓疾患、肝臓や腎臓、血液疾患、ホルモン異常、薬剤性などがあります。
以前何かの講演会で、乾燥肌によるものが多い、演者は述べていましたが、
私は、皮膚に何も出来ていないのに乾燥肌(カサカサ)はおかしいと思いました。
日常診療で皮膚掻痒症はよく経験しますが、やはり鉄不足が圧倒的に多いです。
血液検査をしてみると軽い貧血か、
ヘモグロビンが正常にも関わらず、フェリチンが基準値内でも低値の方がほとんどですが、
鉄不足=かゆみという認識は医師も患者さんもあまりないため、放置されていることがほとんどです。
皮膚は内臓の鏡と言います。
多くは内蔵の病気による皮膚の変化というイメージがありますが、
病気になる前からすでに栄養障害という異常は誰でも始まっており、その影響でかゆみや皮膚の変化があらわれます。
介護生活
こんにちは、院長の栗木安弘です。
最近認知症患者さんの介護責任に関する裁判があったり、
認知症患者さんの診察や介護されている家によく往診に行きます。
介護されている家族は食事介助や病院に連れて行くなど、心身共に苦労が多いと思われます。
認知症には予防体操なども勧められていますが、効果も定かではありません。
栄養的に考えれば、
脳も酸素や栄養で養われており、酸素や栄養が少なくなれば脳の機能低下を生じます。
そのための対策として、
脳の酸化や糖化を防ぐために抗酸化対策や糖質の過剰摂取を控える。
脳への血流を確保するため、軽い貧血でもを放置しない。血圧も下げ過ぎない。
脳細胞は糖質(+ケトン体)、脳神経はコレステロールが必要であるため、血糖を下げ過ぎない、コレステロールを下げ過ぎない
といったところでしょう。
こうした栄養障害は加齢によるところもありますが、食事内容、消化吸収力低下(個人差)や、
胃酸抑制剤、血糖降下剤、コレステロール低下薬といった過剰な薬剤の長期服用も要因となります。
病気の原因ははっきりしないことが多いようですが、
やはり日々の食生活や薬の長期服用の積み重ねによる栄養障害も一因と私は考えています。
〇〇患者の1例
こんにちは、院長の栗木安弘です。
先週土曜日、皮膚科地方学会がありました。
大阪地方会
私も発表いたしましたが、やはり普段の栄養の会とは異なり、皮膚科の先生方の前ではとても緊張しました。
学会発表前にはいろいろな先生方の発表を拝聴いたしましたが、
私のように日常診療での工夫といった内容ではなく、
多くは、珍しい疾患、難渋した症例など、
“〇〇という1例”という内容ばかりが多くみられました。
こうした内容が多いのは、発表されている先生方が
稀な疾患や治療が難しい疾患の集まる大学病院や一般病院に勤務されているため仕方がないかもしれませんが、
毎回、診断がどうとか、組織像がどうとか、治療や術式がどうとか、統計や割合がどのくらい、
といった議論ばかりで、「病気しか対象にしていないなぁ」という印象も受けました。
本来は“〇〇になった患者さんの1例”として
病気ではなく病人あるいは、
病気になった背景(おもに栄養代謝障害)に着目した内容や議論も行ってほしいと思いました。
糖代謝と栄養
こんにちは、院長の栗木安弘です。
先週土曜日は大阪で栄養の勉強会がありました。
おもに糖代謝がテーマで、
①糖質とは
②糖代謝と血液検査
③症例検討
④糖尿病と栄養
に関する内容でした。
私も勤務医のころはよく糖尿病の方を診察しました。
足の傷がなかなかよくならない
足の傷が再発を繰り返す
足の壊疽が進行・切断
感染症を繰り返す
かゆみや湿疹がよくならない、乾燥がひどい
といった方が大勢おられ、しかも血糖のコントロールは良好にもかかわらず、よくならないのが不思議でした。
今考えればこれはもう栄養代謝障害の影響だと理解できますが、
当時はそんな栄養の知識はなく、年のせい、仕方ない、医療の限界として考えて割り切っていました。
栄養代謝を勉強すれば、糖代謝(糖尿病)はタンパク質・脂質・ビタミン・ミネラル代謝と歯車のようにつながっています。
しかし現状では糖代謝だけを無理やり調整しているだけで、糖尿病の患者さんの多くが栄養代謝障害に陥っています。
糖尿病が減らない理由は、脂肪の多い欧米型の食事と言われていますが、
血糖値だけを抑える治療、カロリー中心の食事・栄養に指導についてもう一度見直すべきかと思われます。
高齢者に栄養を。
こんにちは、院長の栗木安弘です。
クリニックを受診される高齢者も多く、往診でも高齢者をよく診ています。
高齢者には必ず血液検査結果をみて栄養状態の確認をおこない、
不足した栄養に関しての食事指導やサプリメントの摂取をおすすめしています。
健康に気をつけている高齢者は必ず何らかのサプリメントや健康食品を飲んでおられますが、
血液検査結果から判断すれば効果はあまり出ていないという印象があります。
やはり高齢者には出来るだけ口から食べていただけるように、
消化吸収対策と吸収のよいサプリメントをおすすめしています。
こうしたサプリメントを飲んでからは、
「毎年出ていた手荒れが起こらない」
「以前よりも元気になった」
「動けるようになった」
「風邪をひきにくくなった」
「白髪が消えた」
「床ずれがよくなってきた」
という方もおられました。
食事だけでは十分な栄養は摂取できず、高齢者も含めほとんどの方が栄養障害です。
さらに薬物の長期服用も栄養障害を助長させるため、
個人的には薬をあれこれ飲むよりはサプリメントでの栄養補給をおすすめしたいと思います。
ペンキ屋だけしたくない。
こんにちは、院長の栗木安弘です。
皮膚科クリニックと言えば、
通常の皮膚科診療や手術や光線治療といった保険診療だけでなく、、
レーザー治療や美容処置などを自費診療を取り入れるクリニックが多いようです。
流行っているクリニックや新規クリニックでは、
美容・エステルームを併設したり、何台も美容・レーザ機器を置いているクリニックもあります。
患者さんのためにさまざまな処置を施してあげることは多いによいですが、
私自身は、皮膚疾患の治療にしろ美容目的にしろ、皮膚は内臓の鏡ですので、
皮膚の修繕は体内環境(栄養状態)の改善が必要と思っています。
今までよくならない、よくなったり悪くなったりの繰り返し、ぬり薬ばかりの皮膚科診療に不満を持たれている患者さん、美容処置のトラブルを実感しているからこそ、皮膚に対しては内面からの栄養アプローチが必要と感じています。
医学は専門性が高いので皮膚科も皮膚だけの対応がメインとなりますが、
私自身は医学を学んだものとして、
栄養代謝(生化学)や内臓疾患と栄養や皮膚の関わりを十分理解して内側から対応したいと思っています。
がんと芸能人
こんにちは、院長の栗木安弘です。
昨日のMrサンデーでは、がんで亡くなられたレギュラージャーナリストの追悼番組でした。
亡くなる前の姿は別人と思うほど痩せ細り、杖をついて苦しそうにされていました。
今までいろいろな芸能人ががんで亡くなっていますが、
i井さん、K嶋さんなど亡くなった方はのほとんどが痩せ細っています。
逆にがんを告白しても元気に活動されている方はあまり変わらないご様子です。
このブログで何回もお伝えしていますが、
がんになった場合、がんで亡くなるのではなく、がんに栄養を摂られて、その合併症(+強い治療)で亡くなります。
がんになった芸能人をみれば分かりますが、
延命するためには、できるだけ体重が減らないような栄養管理が必要となります。
がんになった場合、本人の気力や強い意志、家族の支え、も必要ですが、
がんと免疫・栄養代謝といった面も科学的に理解して対応すべきかと思われます。
食が病気をつくる。
こんにちは、院長の栗木安弘です。
個人的には食は、見た目と味が優先され、
さらに人と人をつなぐコミュニケーションツールであると思っています。
もちろん食事は栄養や体に良い成分も摂取できますが、
それだけでは不十分であること、そして食事内容や食べ方により体によくない影響を及ぼすことは、
栄養療法を学んでこられた方は十分ご存じかと思います。
しかし現状は、テレビやCMではスポンサーの配慮により、
あの食材が体によい、この食品が○〇に効果があるなど、食のよい面ばかりが連日強調され続けています。
食べるというのは他の動植物の生命を奪い、食材に変え、己の生命を維持することですが、
世の中そんな自分の都合の良い話ばかりではなく、食べ続けることで老化進行(しわシミ)や病気(皮膚疾患)もつくります。
例えば、毒や有害成分・重金属の蓄積、食物アレルギー、糖化・酸化、添加物の害などがあげられます。
食のデメリットをできるだけ最小限にして健康でいるためには、やはりサプリメントも必要なのかもしれません。

皮膚が教えてくれる。
こんにちは、院長の栗木安弘です。
皮膚の変化や状態を診るのが皮膚科診療の基本です。
他の先生はあまりされないとは思いますが、
私は専用のルーペを使って、患者さんの皮膚に顔を接近してよく診察していますが、
これも皮膚の変化を詳しく確認するためです。
以前こうした診療で判断が付かなかった皮膚疾患が判明したこともあって、以後このスタイルで診察しています。
皮膚の変化は非常に多彩です。代表的な変化として、
丘疹(ブツブツ)、紅斑(赤い)、亀裂(ひび割れ)、鱗屑(カサカサ)、湿潤(ジクジク)、苔癬化(ゴワゴワ)、色素沈着があります。
こうした変化の組み合わせを診て、アトピーやフケ症やニキビなど診断しますが、
一方で皮膚も内臓の一部であるため、
その変化の背景には必ず体内の栄養障害があることを念頭に置いています。(栄養障害の確認は血液検査)
栄養療法は不足した栄養素をサプリメントで補給をするわけですが、
同時に栄養障害の原因となる食事の乱れ(糖質過剰)以外に、
消化管、肝臓、貧血といった栄養の吸収・代謝・運搬に関わる臓器の栄養改善も必要となります。
病気の診断も重要ですが、
皮膚科医として詳しく皮膚を診ることで、皮膚の変化を体の異常のサインとして捉えて対応したいと思います。

血液を作る。
こんにちは、院長の栗木安弘です。
血液は骨髄というところで、
ビタミンA、ビタミンB群、鉄、タンパク質から作られるため、
こうした材料が少なければ貧血や血液疾患も発症しやすくなります。
現行の保険診療では、
貧血に対して鉄剤やビタミン剤の投与、
大量出血や重症の貧血には輸血、
血液疾患に関しては化学療法や骨髄移植、
という処置が行われますが、輸血による感染症や拒絶反応、薬の副作用というリスクもあります。
そのため緊急時以外は、足りないから入れるのではなく、
造血に必要な材料を入れてスムーズに血液を作っていくという発想も必要です。
どのような疾患でも、まず貧血をはじめ、血液の状態をよくすることが基本です。
やはり血液が少なければ、薬も栄養も臓器に運べませんし、いくら血管を広げても血流も悪くなります。
さらに血液、血流がなければ、皮膚をつくるための材料も不足し、皮膚が弱くなり、容易に皮膚の異常や変化があらわれます。