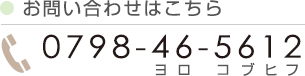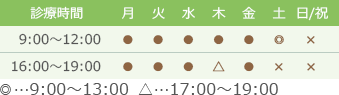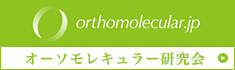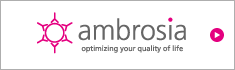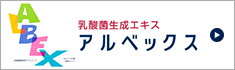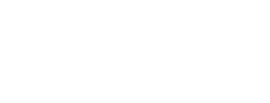寄り添うアトピー治療
こんにちは、院長の栗木安弘です。
少人数でしたが、土曜日は久々の皮膚科研究会でした。
アトピー性皮膚炎に対する精神アプローチとデュピクセント治療についての内容でした。
特に精神アプローチについては、アトピー性皮膚炎が生じている背景や問題点を、
診療の対話を通して引き出して解決するという内容でした。
私はさっぱり分かりませんでしたが、心理とかメンタルケアが好きな医師は非常に興味深い内容だったかもしれません。
ただこうした会話テクニックは、患者さんを誘導する治療の一環ですので、
個人的には心のこもった対応ではなく、
「寄り添うアトピー治療」という研究会のテーマとは少し違ったような気がしました。
個人的には血液検査で科学的に評価して、医師も患者さんも共有できる栄養療法をお勧めしたいところです。
しかし、学会ではアトピー性皮膚炎の精神療法は受け入れられても、
栄養やサプリメントには拒絶反応を示される皮膚科医が多いようです。
栄養相談
こんにちは、院長の栗木安弘です。
クリニックでは、診察時間以外に栄養相談という予約枠で、
血液検査の説明や栄養療法のご相談を行っております。
特に血液検査は、検査項目の意味を理解した読み方(深読み)で、
自身の栄養の問題点を把握していただくようにしております。
血液検査というのは基準値に入っておれば、「異常なし」と短絡的に判断されます。
しかし、病気のあるなしに関わらず栄養の問題が存在する限り、
治療がスムーズに進まなかったり、体調不良や倦怠感や痛み、皮膚トラブルを訴える方も少なくありません。
以前、栄養の勉強会で、
「医学部からこうした生化学的な栄養の読み方を教えるべきである」
と誰かがおっしゃっておられました。
病気に対する決められた対応だけでなく、栄養障害にある病人の理解と対応も必要です。
鉄循環の理解
こんにちは、院長の栗木安弘です。
鉄不足では、
ぶつぶつしたかゆみ、かぶれ、ニキビ、ヘルペスなどが生じやすくなります。
鉄の評価は血液検査で行いますが、ただ単に鉄が不足しているケースだけなく、
鉄は十分あっても、うまく使われていないケースもあります。
こうしたケースは脂肪肝や慢性炎症などを合併している場合が多いようですが、
最近はキレート鉄による影響などもあります。
鉄循環の評価はヘモグロビンやフェリチン(多くは高値)や血清鉄だけでなく、
他の検査項目によって詳細に判断します。
当然、栄養対策は鉄補充が優先ではなく、
鉄がうまく循環しない要因を見つけて対処することが必要となります。
普通の皮膚科じゃない
こんにちは、院長の栗木安弘です。
皮膚科といえば、レーザーや美容医療を取り入れたクリニックが大半です。
それはそれでいいとは思いますが、昔から皮膚は内臓を反映する臓器です。
そのため皮膚の変化や異常の多くは内臓から生じています。
そして病気のほとんどが何らか栄養の問題が背景にあるとすれば、
体内の栄養の問題を是正することが皮膚トラブルや病気の根本的な対策と考えます。
表面ばかりの対応だけなく、体の仕組みや病気と栄養の関わりといった、
内側に目を向けた知識と対応が皮膚科医には必要と考えます。
安価でお手軽な治療であれば通常の皮膚科でいいでしょう。
しかし、なかなかよくならない、病気の原因を知りたい、根本的な治療をご希望の方は是非クリニックにお越し下さい。
サプリ代
こんにちは、院長の栗木安弘です。
クリニックで栄養療法を実践されている患者さんのサプリメント代は平均は1〜3万/月というところです。もちろん、
栄養療法やサプリメントに大変興味がある
早く症状や病気を改善したい
病気の予防、アンチエイジング
など、目的によって異なりますが、なかには10万前後/月の方もおられます。
私自身は栄養療法が半分趣味ですので色々飲んでいます。
また新しいサプリメントも安全な人体実験と思って一通り試しています。
車や洋服や旅行、健康診断や人間ドックなど、何にお金をかけるかは個人の自由ですが、
私自身は筋トレ代も含めて、予防や見た目にお金をかけたいと思います。
胃がん
こんにちは、院長の栗木安弘です。
先日、ピロリ菌についてのZoom勉強会に参加しました。
栄養療法に出会う前までは、ピロリ菌には全く関心がなく、
好きなもの食べて、やりがいや使命感だけで無理して仕事をしておりました。
当然こんなことしておりますと不調も生じます。
そのなかで、特にひどかったのは空腹時の胃痛でした。
薄々は胃炎か胃潰瘍だと思っていましたが、
検査も面倒だったので、適当に胃薬を飲んで誤魔化していました。
栄養療法で血液検査等を学んでいくと、やはり検査でピロリ菌が陽性でした。
除菌をして栄養療法を続けていくうちに、
ピロリ菌も減少、胃の炎症や症状もなくなりました。
元々尿酸が低いがん家系だったので、放置したままだとおそらく胃がんになっていたでしょう。
栄養療法を学んでよかったなぁとつくづく思います。
食の講演会
こんにちは、院長の栗木安弘です。
栄養科学博士のオーガスト・ハーゲスハイマーさんの食の講演会に参加しました。
食事を見直して健康を取り戻すことは重要ですが、
今はさまざまな食に関する情報が溢れているため何を信用していいのか分かりません。
そういった疑問や知識の整理について、体本来の働きから考える理想的な食事を、分かりやすく楽しくお話しを聞かせていただきました。
良質な油、タンパク質と緑黄色野菜、糖質は減らすことが理想的な食事です。
ただ、これだけ糖質や加工食品が溢れている世の中で実践するのは難しく、演者は80%の努力でいいとのことで、ご自身も1回/週はピザやパスタなどを堪能されています。
世の中にはさまざまな食事療法がありますが、オーソモレキュラーはこうした食事の見直しに加え、サプリメント使用することが前提の治療法です。そのため、栄養に精通した医師のもとで定期的な診察や血液検査を行うことが望ましいと考えます。しかし最近は書籍やSNSだけの情報だけで安価なサプリメントを飲まれている方も少なくありません。
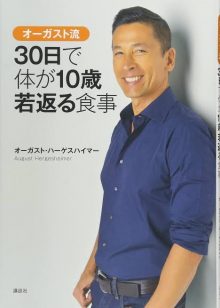
岡本太郎展
こんにちは、院長の栗木安弘です。
普段美術館はあまり行きませんが、こちらは大変興味があって観に行ってきました。
岡本太郎といえば、子供の頃にバラエティ番組を見て、
「独特の目つきをした変わったおじさんだなぁ」という印象しかありませんでした。
作品は大阪万博の『太陽の塔』が有名ですが、
館内には、色彩豊かな多くの絵画やオブジェがたくさん展示しており、
また近鉄バッファローズのロゴまでデザインされていて驚きした。
よく天才は時代が追いついていないと言われますが、
岡本太郎の感性は、今の時代でもまだ追いついていない気がしました。


保湿は外せない
アトピー 性皮膚炎のweb講演会を拝聴しました。
製薬会社主催ですので、最近注目されている新薬の効果をアピールした内容でした。
新薬でアトピー性皮膚炎はよくなっても、
保湿は続ける必要があるということを強調されていました。→いつまで続けるねん。
皮膚科医の頭のなかは、アトピー 性皮膚炎には保湿が何がなんでも必須のようですが、皮膚の仕組みや代謝を理解すれば、本来は体の内側から潤いを取り戻すことも重要です。
お偉い先生方は乾燥肌がアトピー性皮膚炎の原因と考えておられるようですが、
保湿のほとんどしない発展途上国や原住民ではアトピー性皮膚炎はほとんどいません。
そういったところから病気の原因を探っていく必要があるかもしれません。
サブスペシャリティ
こんにちは、院長の栗木安弘です。
皮膚科の中でも、さらに専門性を高めるためにサブスペシャリティーがいます。
私自身も、病院勤務の頃は“自称”、
アトピー、脂漏性皮膚炎、褥瘡、皮膚潰瘍、皮膚外科、皮膚病理診断を専門や得意分野としており、こうした学会や講演会などによく参加しておりました。
そして勤務医のまま、専門性を高めて医者人生が終わると思っていました。
しかし、栄養療法に出会ってからは、
栄養が専門となり、クリニックを開設し現在に至ってこのようなブログを書いております。
当初、考えていた人生とは大きく変わってしまいましたが、
栄養を専門にすると、皮膚科診療だけでなく、
自身や家族の健康向上や予防など、役立つことばかりです。
栄養療法というわけのわからん治療をして、
同業者から批判もありましたが、この道を選んでよかったなぁと思います。