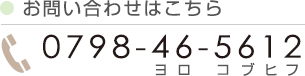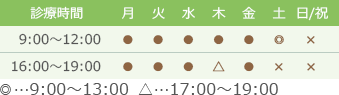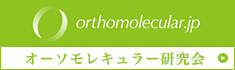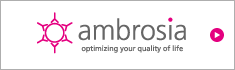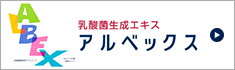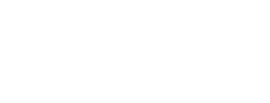新薬
こんにちは、院長の栗木安弘です。
最近アトピー性皮膚炎に対する新薬が発売されました。
アトピー性皮膚炎の初の抗体医療薬で、
おもに重症や難治のアトピー性皮膚炎を対象とした治療薬となります。
こうした薬に関連した講演会なども主催され、
新薬が出て、治療の選択肢が増えて、喜ばしいと思う医師が大半ですが、
素直ではない私は手放しでは喜べなかったです。
冷静に考えれば、こうした新薬は、
安全性や長期の副作用はどうか?
妊娠、授乳、小児の適応は?
コストは?
いつまで続けるのか?
などいくつかの課題や問題点も残ります。
ガイドラインや論文や学会では、医師の大半は、病気の治療=薬しか頭にありません。
今後どのような新薬や画期的な治療薬が開発されても、これら全てリスクのある対症療法であることを理解すべきです。やはり人の体の根幹である食事(バランスや野菜中心だけなく)や栄養に目を向け、本来の治癒力を引き出すアプローチが必要かと思われます。
オーソモレキュラー一般講演会
こんにちは、院長の栗木安弘です。
昨日は東京有楽町でオーソモレキュラー一般講演会の演者として参加させていただきました。
猛暑の中、会場には大勢の方が集まっていただき感謝感謝でした。
私以外に分野の異なる医師が疾患別にオーソモレキュラーの取り組みや症例紹介をされており、自身も非常に勉強になり、オーソモレキュラーの奥の深さと医療における必要性を益々感じました。
保険診療の中心の医療ですが、医療が発展しているにも関わらず医療費は年々上昇し、病気は一向に減りません。薬の使い方、新薬や新たな治療法に期待するのも良いでしょうが、
もう一度自身の食生活や栄養状態に周囲に目を向けることも重要です。
講演会の中でも強調させていただきましたが、
何を食べるかも必要ですが、どのような栄養をどのくらい摂取しなければならないかを理解して実践することで心身や生き方まで変わります。

コードブルー観てきました。
こんにちは、院長の栗木安弘です。
『劇場版コードブルー』を観てきました。
救急医療の現場でドクターヘリに搭乗する医師の成長を描いた作品です。
救急医療こそ医療本来の役割だといつも思っていて、
医者になって皮膚科から救急科に転科したいと思った時期もありました。
救急医療のように、事故や災害や急性疾患は対症療法でもいいですが、急性期が過ぎたり、慢性疾患に対しては薬で症状や検査異常値を抑えていくことが永続的に続くため、根本的な対応ではありません。病気の予防や再発、薬の副作用が心配、薬を減らしたいという方は、栄養療法をお勧めします。

自分への投資
こんにちは、院長の栗木安弘です。
クリニックで取り扱っているサプリメントは、
栄養療法専門サプリメントで、市場に出回っているものより高額です。
一般にサプリメントはお手軽で安いというイメージがあり、高いサプリメントは敬遠される方がほとんどですが、 サプリメントの原材料、製造加工、濃度、配合などを考えれば、本来は妥当な値段かもしれません。
自身のサプリメント代は月ウン万円しますが、一旦病気になれば、検査治療費・入院費・通院費にいくらお金がかかるか分かりませんし、治療がどのくらい続くのかも分かりません。最近の抗がん剤はめちゃくちゃ高いですし、治療や処置の後遺症、薬の長期服用による副作用も心配です。
病気や寝たきりにになれば家族やクリニックスタッフにも大変迷惑がかかります。
私の嫌いな「早期発見早期治療」が医療常識のようですが、高騰する国民医療費のことを考えれば病気にならない予防策が重要です。
ただし予防は県や国の補償はなく、ある程度自費負担を覚悟しなければなりません。
ロボットや高級車など、精密機械の修理やメンテにはそれ相当の費用がかかるのに、それ以上に精巧なヒトの体がタダや安価でよくなるはずはありません。
月ウン万円とはいいませんが、宝石やバックを買うよりは、せめて1万円くらいでも体に投資をしていただきたいと思っています。

血液検査とにらめっこ
こんにちは、院長の栗木安弘です。
通常、血液検査というのは、基準値よりも高ければ、高脂血症、糖尿病、痛風、肝臓が悪い、○○病の確定、
など病気の判断に使われたり、治療効果の判定にも活用されます。
これは医療機関だけでなく、健康診断や検診などでもそういった見方で判断します。
医者になって、血液検査というのは、病気の診断や程度を確認するためのものであって、その基準値は、昔は正常値と呼ばれ、絶対的に正しい値と思っていました。
しかし栄養療法を勉強すると、血液検査の基準値というのは実は検査会社によりバラバラで、基準値そのものに科学的根拠は乏しい、ということが理解できるようになります。そして基準値に捉われない生化学的な読み方を学ぶことで、皮膚トラブルをはじめ、不調や病気の原因の多くが栄養に起因するものであると分かるようになります。
栄養療法を実践している医師の一人が、
医学部からこうした血液検査の読み方を学ばなければ、
いつまでも病気しか診ない、診断ばかりに捉われたマニュアル治療しか出来ない医者にばかりになると懸念されていました。
クリニックでは皮膚は内臓(栄養)の鏡として捉え、まず皮膚科医として皮膚の変化をよく診ること(それすら出来ていない皮膚科もいますが…)、そしてその変化が栄養状態にどう反映されているかを、毎日血液検査結果とにらめっこして病態を理解するようにしております。
消化管と皮膚
こんにちは、院長の栗木安弘です。
先週日曜日は品川で栄養セミナーでした。
消化管と皮膚というテーマで、自身もクリニックで実践している内容やノウハウをご紹介させていただきました。
皮膚のトラブルをお持ちの方のほとんどが、何らかの栄養の問題があり、その一因が消化吸収にあります。皮膚を根本的によくするためにはやはり消化管アプローチが皮膚科診療は必要となります。
しかし実際は、皮膚科を受診される多くの方は、内臓云々よりも、
一発でかゆみが取れる塗り薬
魔法のようにきれいになるクリームや塗り薬
といったところを期待されます。まして食事や保険の効かない高額なサプリメントを飲んで皮膚をゆっくり直すという発想は栄養療法をご存知ない患者さんはなかなか理解しにくいところです。
塗り薬も否定はしませんが、
「塗るのをやめると出て来た」
「塗り薬が合わない」
「塗れない、続かない」
「薬を使いたくない、頼りたくない」
という方は皮膚に対する見方や発想をを変えることが必要であり、
できるだけこうしたお手伝いができるような皮膚科診療を目指したいと思っています。
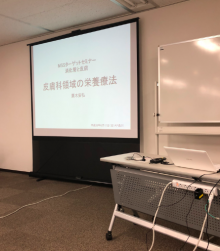
かゆみと栄養
こんにちは、院長の栗木安弘です。
“かゆみ=アレルギーや乾燥”というイメージをお持ちの方は多いかもしれません。しかし食物アレルギーやじんま疹などは食べ物が関係するように、かゆみには食事や栄養も深い関わりがあります。
かゆみを生じる原因にはいくつかあり、食事や栄養に関して言えば、
①糖質過剰
②コラーゲン不足(材料であるタンパク質・ビタミンC・鉄不足、糖質過剰による糖化)
③遅延型食物アレルギー
④刺激物、アルコール、コーヒー
⑤粗悪な油(植物系、古い油)の過剰摂取
などが挙げられます。
かゆみの原因は個々で異なりますが、自分自身では、卵や糖質過剰やコーヒーを飲むと数日後にかゆみが強く現れます。
かゆみ神経は、その電気信号の伝達に、ビタミンB群、鉄、カルシウム、マグネシウムなどが関与するためこうした不足もかゆみを引き起こしやすい原因となります。
かゆみ止めのお薬が効かない、効きにくい方は、あれこれ薬を変えるよりは、まず普段の食事を見直すこと、できれば不足している栄養素をサプリメントで摂取することで、即効性はありませんが、お薬の効きがよくなる、かゆみの軽減や予防に繋がります。
最後にかゆみは「できるだけ掻かない」ことが常識美徳であり、皮膚科診療でも「掻いちゃだめ」とよく指導されます。しかし実際はかゆみは我慢できないし、掻くことは快感です。犬も猫も掻いているのに人間だけがかゆみを我慢して、何かを塗っていることも不思議でなりません。
皮膚が丈夫であれば、掻いて傷ついてもすぐに修復はされます。
栄養と学会
こんにちは、院長の栗木安弘です。
時々皮膚科学会で栄養に関した内容を発表させていただいております。
こうした内容を応援していただける医師もいる一方で、
あまり快く思わない医師も実際におられます。
受け入れない理由としては、
エビデンスに乏しい。
持論、思いつきでしかない。
など学会の趣旨とは異なることが理由の一つとなります。
栄養はエビデンスではなく、ある意味生化学であるため、すでに医学部でも習っている事で、エビデンス以上に広く認知された内容であります。また、どのような疾患や治療法でも最初は持論や思いつきになります。(偉い人が言えば仮説や素晴らしい発想と絶賛されるが…)
体の仕組み、病気の成り立ちには生化学な異常が存在し、その是正には食事やサプリメントを用いたオーソモレキュラーが必要となります。しかし医者の多くは、エビデンス、診断→治療(=薬)という方程式を医学教育や学会で刷り込まれており、オーソモレキュラーを理解させるためには、馴染みの薄い生化学、栄養代謝やサプリメントの正しい知識が必要となります。
先日行われた抗加齢学会では、栄養や食事、遅延型食物アレルギーやオーソモレキュラーが当たり前のように取り上げ、討論されており、また参加者もさまざまな科や分野の専門家ばかりでした。身体や病気を対象とする同じ医学会でも随分違うなぁと感じました。
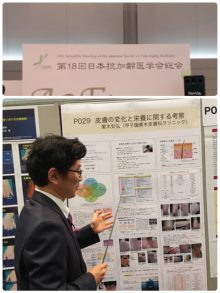
皮膚科の基本
こんにちは、院長の栗木安弘です。
皮膚科の基本は「皮膚を診る」ということですが、
このことが皮膚科の中では軽視されている方向に行っている気がします。
クリニックを受診した患者さんは時々、
「前医の皮膚科は診てくれなかった」
「診ないでぬり薬だけ処方された」
など皮膚科医として耳を疑う不満の声も聞きます。
また最近ではアトピー性皮膚炎で盛んにおこなわれるTARC(皮膚の炎症の程度を表す検査)ですが、皮膚の状態よりもむしろこうした検査結果を優先に外用の指示が行われます。
さらに皮膚疾患の確定は肉眼的な判断ではなく、皮膚の病理組織検査により行われ、これがないと学会・論文等では認められないことになっています。
肉眼的に「診る」という最もアナログ的な対応が皮膚科の基本であるにも関わらず、なんだか病気の診断や程度ばかりにこだわり、それに関連した検査ばかりを重視する傾向になっています。
医学は診断・治療が基本で、ほとんどの皮膚科医はこうしたプロセスで診療を行いますが、皮膚は内臓(栄養)の鏡ということを忘れてはいけません。
病気という実態のないものを診断するのもいいでしょう、しかし実際目に見える皮膚の詳細な変化を視診や触診で確認し、その変化の内面に存在する栄養代謝障害という原因に対応することもこれからの皮膚科診療に必要なアプローチだと思います。
おまけのビタミン剤
こんにちは、院長の栗木安弘です。
数年前にも学会発表しましたが、ビタミン剤を処方する場合、
多くはビタミンの過不足は評価せず、症状から判断され、
治療の足し、副作用もなく効けばラッキー
という感覚で、処方されることがあります。
自身も以前はそういった感覚に加えて、“保険適応がある”ということからサプリメントよりも保険のビタミン剤がベストであると思っていました。
しかし、栄養療法を理解すれば、
ビタミンB群は合成より天然で8種類全て摂取する方が効果的
ビタミンB群の活性には核酸が必要
保険のビタミンEは合成で代謝されない
ビタミンC単独よりはビタミンPやαリポ酸と同時摂取が有効
などなど、単体の合成ビタミンよりも、きちんと作られた天然サプリメントの方が圧倒的に効果があることがわかります。
さらにビタミン剤の歴史は古く、約40年前に承認されたものが多く、栄養代謝が解明されれば改良されてもいいはずですが、コストもかかるし、特許が得られないことから、当時作られた内容のままです。
診療では保険の安いビタミン剤を希望される方や、おまけ感覚で処方する医師もいますが、やはり栄養代謝を理解した医者としては、効果や体に対する働きから考えるとサプリメントの方がベストとなります。