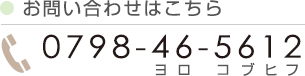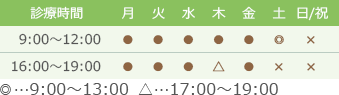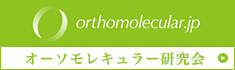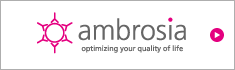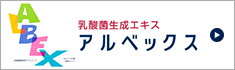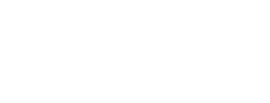本
こんにちは、院長の栗木安弘です。
本は好きなのでよく書店に行きますが、
皮膚科の関連の本ではなく、栄養療法・栄養代謝に関する本をよく購入します。
病院勤務の時は、
「皮膚・皮膚科についてしらないことが無いように」
「誰にも負けない皮膚科の知識を得る」
という強い思いから、
皮膚科の本や医学雑誌を片っ端から買っていて、病院時代の医局の机には、書店の皮膚科コーナーよりも多くの本や雑誌が陳列しておりました。(下写真)
しかしこれだけ本があって、毎日読んで実践しても、結局はあまりよくならず、日進月歩の医学においては、診療の問題点を何一つ解決することができませんでした。
その後、栄養療法を知って、皮膚以外の栄養代謝や生化学関連の本を読むようになり、栄養療法の知識を持つようになってからは、日々の診療の疑問の解決と応用が可能となり、今ではそちらの本ばかりが増えています。
問題解決は、自分自身の世界を広げることだと誰かが言っていましたが、各科の専門性が強い医学ではまさにその通りだなぁとつくづく感じます。
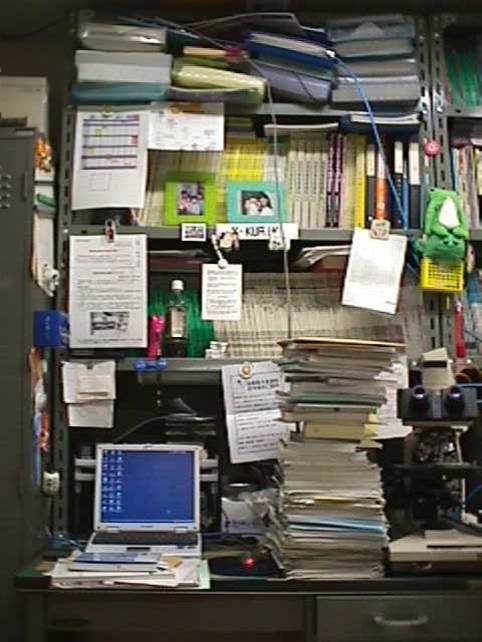
中部支部総会IN京都
こんにちは、院長の栗木安弘です。
この土日は京都で開催された日本皮膚科学会中部支部総会に参加してきました。
このため土曜日は臨時休診となり、患者さまには大変ご迷惑をおかけしました。
学会では私自身も、
ポスター発表は「亜鉛と皮膚疾患」
口頭発表は「保湿の功罪」
という演題で発表させていただきました。
亜鉛と皮膚の関係、血液検査での評価、症例報告などを供覧し、多くの先生方に興味をもっていただきました。
保湿剤に関しては、医療現場におけるヒルドイドの乱用についての問題点を指摘し、同じような意見をもっておられる先生方や関係者と意見交換もできました。
全体的には小規模な学会でしたが、個人や講演などいろいろなお話を聴くことができて、勉強になる2日間でした。
ただ、いつも申し上げているように学会というのは、
診断や薬物治療や研究、まれな症例・難渋例などを中心に発表や討論がされることばかりで、
個人的には、栄養代謝というものを理解して、栄養をもっと応用すれば、
「臨床や研究での疑問点の解決」
「もっと改善率も上がるだろう」
という症例や講演もいくつかありました。

カルテ記載
こんにちは、院長の栗木安弘です。
研修医の頃は、
上司の先生のカルテ記載をお手本に、皮膚所見を英語でカルテ記載をしていました。
scarly erythema
erythematous papule
doing well
status quo
など皮膚科医は誰でも知っている専門用語を必死で覚えていた記憶があります。
一般病院勤務に変わってからは、なぜかカルテは日本語ONLYで記載しようと決意して、ひたすら丁寧に書いていましたが、字が汚くて後から怪文書のようなだとなじられたこともありました。
開業してからは電子カルテとなり、キーボードでの皮膚所見の打ち込みとなり、勤務同様にできるだけ日本語で詳細に記載しようと心がけています。
皮膚科医は皮膚を診るのが基本です。
いつも強調しているように、目に見える皮膚の変化は、病名という実態のあるものではなく、赤い、ぶつぶつ、ジクジク、カサカサなど変化そのものです。そしてその変化の背景には体のどういった異常が隠されているのかを把握する必要があります。
自分自身が心がけているのは、皮膚の病名だけでなく、こうした皮膚の変化を詳細に確認し、体内の栄養状態の把握することで、そのためにも皮膚の所見を一行一言や簡単な英語表記ではなく、できるだけ詳しく記録したいと思っています。
皮膚が弱い
こんにちは、院長の栗木安弘です。
かぶれ、手荒れ、金属アレルギー、アトピー、乾燥、かゆみ・湿疹、各感染症、
などすべての皮膚トラブルは、おおざっぱに言えば、皮膚が弱くなることが原因です。
皮膚が弱いと本来の機能である皮膚バリア機能や免疫機能が低下します。
ですから皮膚本来の機能を取り戻し、皮膚を強くすることが重要ですが、
皮膚が弱いということなどは科学的に証明することは不可能で、
多くの場合、皮膚強くするという対策ではなく、外から加わる刺激やアレルゲンばかりを追究・除去、そして皮膚表面に何かをぬって守ろうという発想しか皮膚科医にはありません。
皮膚の本来の機能を取り戻し、皮膚を強くするためには、
栄養療法の創始者であるライナス・ポーリングが提唱したような、至適量の栄養補給をしなければなりません。
至適量とは、各組織や臓器が本来の機能や治癒力を発揮する栄養量であり、通常は食事や体内で生合成される栄養量では不十分であると言われています。
ポーリングは精神疾患における脳内の至適量について主張しましたが、
私自身は皮膚も同様だと確信して、サプリメント補給による栄養療法をおすすめしますが、「皮膚はぬり薬」というイメージや、栄養が皮膚に至る経路(胃腸、肝臓、貧血)に問題ある場合も多々あり、皮膚を根本的に治すには時間も費用もかかります。
診療ではサプリメントばかりすすめていることが多いかもしれませんが、
保険適応の薬(ぬり薬)は対症療法ばかりです。
皮膚科医として、ぬり方をはじめ皮膚科薬の使い方・工夫、美容処置なども必要ですが、やはり健康で美しい皮膚や体を取り戻すためには、まず栄養療法が必要なアプローチだと確信しています。
ピロリ菌検査
こんにちは、院長の栗木安弘です。
クリニックでもピロリ菌検査(自費)を実施しております。
ピロリ菌検査をご希望される方だけでなく、
慢性じんましん、赤ら顔、アトピー、かゆみ、お腹の調子が悪い方、
あるいは採血結果からMCVが高い、微小炎症、
または栄養的に合わない、おかしいデータをみたとき、
など患者さんの状態や採血結果に合わせて、ピロリ菌検査をおこなっており、
陽性の場合、近隣の消化器内科に紹介し除菌を実地していただいております。
除菌することで、
胃の調子がよくなった方だけでなく、かゆみや赤味が減ったという方もおられ、
栄養療法に出会う前は「ピロリ菌なんか皮膚科と関係ない」
と思っていましたが、私自身の皮膚科診療ではもうピロリ菌検査は欠かせない検査となっています。
ピロリ菌もそうですが、栄養療法を勉強するようになって、
皮膚以外の知識を学んだり、皮膚科以外の先生方と情報交換することが、
実は日々の皮膚科診療に大いに役立つことを強く実感します。
血液検査の読み方
こんにちは、院長の栗木安弘です。
昨日は大阪で歯科衛生士さん対象のオーソモレキュラーにおける血液検査の読み方の講義をさせていただきました。
歯科ではあまりなじみのない血液検査やオーソモレキュラー療法ですが、非常に熱心にに興味深く聴いていただきました。
講演後は、
「見方が変わった」
「靄が取れたような感じ」
「面白い!もっと知りたい」
という意見をお聞きし大変うれしく思いました。
血液検査の深読みはオーソモレキュラーの基本です。
自身もオーソモレキュラーに出会ったきっかけは、
当時勤務していた医局に置いてあった某雑誌に掲載されていた深読みの特集記事でした。あの日あの時の出会いがなければ、開業もせずあのまま一生勤務医で過ごしていたかもしれません。
血液検査の読み方、オーソモレキュラーの出会いなど、ちょっとした出来事がその後の治療方針、体や人生を大きく左右することになります。

2分診療
こんにちは、院長の栗木安弘です。
アトピー性皮膚炎患者の約30%が、平均2分以下の診察時間であるという報告があります。
http://newswitch.jp/p/9828
診察時間が短いのが悪いというのではありませんが、
これでは納得いく診察は難しいかもしません。
医療の基本が診断→治療ですので、
治らないアトピー性皮膚炎と一旦診断されれば、お決まりのような治療が永遠と続きます。
まぁ長年のアトピー性皮膚炎の患者さんは、
最初から皮膚科医には治せる期待は抱かず薬だけもらえればいいという患者さんも少なくありませんし、 皮膚科医もガイドラインで決められたステロイド外用剤を処方すれば診察時間も短くすんで、その他多くの患者さんの診察もできます。
皮膚科の診療単価が他の科と比べて低いので、時間をかけ、じっくり診て、きちんと説明する本来の診療スタイルが、逆に経営面に首を絞めるという自体にもなっています。
アトピーという診断も適切な外用指導も必要ですが、皮膚の変化は目に見えます。
アトピーという病名の原因は分からなくても、なぜその変化が生じているかを皮膚科医は考えて、きちんと説明しなければいけません。
クリニックでの栄養療法
こんにちは、院長の栗木安弘です。
クリニックは他の皮膚科と比べて、栄養療法を軸に皮膚科診療を行っています。
そのため、どうしてもぬり薬のぬり方や使い方、スキンケア指導よりは、栄養の話を重視してお話することが多くなります。
とくに長年皮膚でお悩みの方、ぬるとよくなるがやめると出てくる、アトピー性皮膚炎をはじめとした重症皮膚疾患の方は血液検査や栄養のお話をじっくりさせていただきます。
しかし中には、診察をしてみると、実は診断が間違っていたり、今までぬっていた薬が合わなかったり、という方も時々おられ、栄養療法を行う前に治療法を変えてよくなる方も意外とおられます。
栄養療法を行うことで心がけていることは、
まず、できるだけ保険の範囲で治療できるものはする。
つまり正しい診断と適切な治療を軸にして、根本的なところは希望により栄養療法を併用していく。
説明は、こちらから一方的にするのではなく、患者さんの話もよく聴く。
話を聴くことで、その内容や細かい訴え、皮膚や爪など目に見える変化を観察し、栄養状態がある程度推測できる。(確認は血液検査)
サプリメントについては継続していただけるように金銭的な部分も考慮する必要もあります。
栄養療法を謳っているクリニックの多くは栄養解析を行い、
栄養解析レポートに基づいてサプリメントを選択することがほとんどです。
確かに細かく解析された栄養解析レポートでのサプリ選択がベストではありますが、
実際は、たくさん飲めない(せいぜい2~3種類)、飲むのを忘れてしまう、飲めても金銭的に続かない、カプセルがダメ、顆粒がダメなど、飲むと気持ち悪くなる方、味がまずいなどいろいろ経験します。
栄養療法をご存じで、十分理解されている方は、頑張って続けますが、
個人的には、患者さんの意向をお聞きして、できるだけ継続していただけるよう、負担の少ないように栄養療法をすすめて行きたいと思っています。
誕生日
こんにちは、院長の栗木安弘です。
昨日は誕生日でした。
SNSを通じてたくさんのお祝いメッセージを頂き大変感謝しております。
生まれて~小中高大で24年、医者になって約24年、とちょうど人生半々となりました。
特に後半は山あり谷ありの医者人生で、
振り返ってみると20代は大学病院が中心で、研修医時代は皮膚科を止めようと思った時期もありました。その後は皮膚科助手として重症患者、手術処置、学会などの対応に追われ心身共に疲れ切っていました。
30代は一般病院勤務となり、皮膚科専門医を取得し、日々外来診療、入院加療、手術、レーザーなどを積み重ね、充実した皮膚科診療を勤しんでいました。
ある程度仕事ができるようになると、心の底では、
「病院皮膚科で十分、皮膚科開業医なんか必要ない」
「自身は開業しない」
と決め、勤務医のまま医者人生を全うする人生設計でした。
しかし、栄養療法に出会い、その素晴らしさに魅了され、
栄養療法をどうしてもやりたいという強い思いから、40歳過ぎで開業を決意。
これまで多くの方々にご迷惑をかけ、助けられ、試行錯誤を重ね、
今年で開業7年、ようやくここまで来たなぁという感じです。
考えてみると、仕事そのものは常に綱渡り状態でしたが、幸いにも大きなトラブルや事件、事故、病気もなく、さらに画期的な栄養療法に出会い、私自身とてもラッキーだったと感じます。
これから人生の後半がはじまります。
とりあえず、体が続く限り、皮膚科診療や栄養療法を通して、少しずつ恩返して行きたいと思っています。
皮膚科での栄養療法
こんにちは、院長の栗木安弘です。
ここ何年か学会等で栄養と栄養に関して、何回も学会発表をさせていただいておりますが、
やはり皮膚科の世界では、
ぬり薬・スキンケアが中心
組織診断や手術手技
研究、珍しい症例、難渋例
原因はアレルギー、難しい遺伝子異常
レーザーや美容処置
ということが主流であり、
栄養と皮膚疾患、皮膚を栄養で内面から治すということが、
皮膚科の世界ではまだまだ認識が薄いことを、学会参加・発表しますと大いに実感します。
皮膚は内臓の鏡という言葉も盛んに強調されている方もいるようですが、体内の栄養代謝障害ではなく、専門家が内臓の病気を適切な薬物治療で治すというくらいの認識しかありません。
新しいことはなかなか受け入れにくい医学会ですが、
どこに行ってもよくならない、どうしたらいいのか分からない患者さん、
あるいは日々の診療で行き詰ったり、困っている先生方は、
ぜひ、皮膚と栄養(栄養療法)について学んでいただきたいと思っています。
今後の予定としては、大阪地方会、中部支部総会、歯科医師および歯科衛生士向けセミナー、などで引き続き情報発信を予定しています。