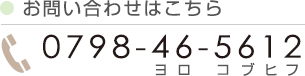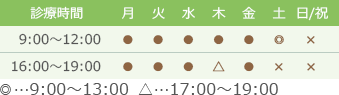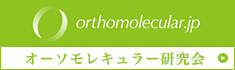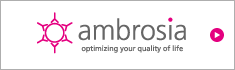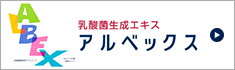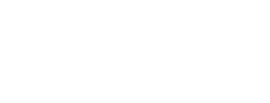高倉健追悼展
こんにちは、院長の栗木安弘です。
先週土曜日、芦屋の大谷美術館で行われている高倉健追悼展に行ってきました。追悼展では過去の映画のダイジェストがスクリーンに映し出されて、思わず見入ってしまいました。健さんの映画は世代的には昭和任侠ではなく、熟年期に入ってから作品をよく観ており、居酒屋兆治、海峡、夜叉が好きな作品です。
黙っていても絵になる健さんですが、それ以上にこの方は、実直、謙虚、思いやり、心遣いといった人として本来の姿を思い出させてくれます。
http://otanimuseum.jp/exhibition_180407.html
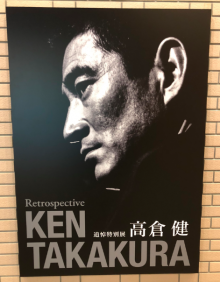
皮膚科のハードル
こんにちは、院長の栗木安弘です。
皮膚のトラブルの多くは内臓に由来しており、
皮膚は内臓(栄養)の鏡という考えのもと、クリニックでは日々診療を行っています。
血液検査では、多くの方に栄養障害を認め、栄養障害の影響がさまざまな皮膚の変化を生じることはほぼ間違いありません。
また栄養障害の原因は食生活だけでなく、消化吸収障害、肝障害、貧血など栄養の消化吸収・代謝・運搬に問題があるケースもあります。
皮膚を根本的に良くするためには、食生活だけでなく、栄養障害の原因である内臓の問題も改善する必要が間違いなくありますが、
専門性の強い医療のなか、皮膚科の医者が、
鉄不足、貧血、肝臓、消化管など栄養や内臓云々の話をしても説得力がなく、また皮膚科で血液検査するというイメージも少なく、どうしてもよく効く塗り薬や正しい塗り方の指導を期待されます。
さらに保険の効かないサプリメントを飲んで皮膚をゆっくりとよくするイメージもほとんどありませんので、栄養療法を理解して実践していただくための皮膚科のハードルというものがいかに高いかというのを常々実感します。
それでも表面だけあれこれするのではなく、内面からのアプローチが本来の皮膚科診療、皮膚の直し方であると確信していますので、しつこいようですが、患者さんには毎回皮膚と栄養に関してできるだけ丁寧に説明をするようにしています。
金属アレルギー(持論)
こんにちは、院長の栗木安弘です。
金属アレルギーに力を入れてやっておられる先生方には申し訳ありませんが、
個人的には金属アレルギーには懐疑的な考えをもっています。
金属アレルギーが疑われると、
まずいくつかの金属を皮膚に張り付けて反応をみるパッチテストがよく行われます。
しかしパッチテストでの判定は科学的数値ではなく、皮膚の反応を医師の肉眼的な判断で行われ、偽陽性や偽陰性、単なる刺激反応もあります。
陽性反応の場合、ニッケルやクロムなど生体にとって必要な金属に反応を生じること自体がやはり納得できず、 反応した金属の含まれた食材を控えるという対策自体も、
消化吸収の仕組みから考えれば、そんな単純なことではないし完璧には除去できません。(仮に完全除去すれば必須金属の不足が生じます)
そしてもっとも疑問に感じるのは、鉄アレルギーがほとんど報告されないということです。生体内でもっとも多い金属であれば反応する確率も非常に高いかと思いますが、全くそのような報告もありません。
勤務医時代も金属アレルギーの検査をして除去指導もしましたが、劇的によくなった方もおられませんでした。
金属アレルギーというのは、基本的には刺激反応であり、やはり栄養障害で皮膚が弱い方は外からの刺激に反応しやすいため、金属にも容易に反応します。
パッチテストを数回すれば確実性が高まりますが、何回もすれば感作の危険性もあります。
最近、鉄不足がニッケルの吸収を促進するという報告もあるように、
https://nutmed.exblog.jp/21984293/
日々診療していますと鉄不足の方は金属アレルギーが多い印象を確かに受けます。個人的には栄養補給により体内および皮膚の機能を高めれば、金属刺激反応は軽減すると思われます。
アドバンスセミナー
こんにちは、院長の栗木安弘です。
昨日は品川で栄養療法における血液検査の読み方の応用編(アドバンスセミナー)でした。
栄養療法を勉強するようになって約10年経ちますが、こうしたセミナーは、毎回新しい発見があったり、忘れていた内容の再確認ができて大変勉強になります。
血液検査の基準値だけに捉われない読み方を理解すると、患者さんの皮膚のトラブルをはじめ様々な不定愁訴や疾患に栄養の問題が存在することが分かります。
ただ単にガイドラインや教科書で決められた通りの診断と薬物治療だけではなく、こうした栄養の問題を解決することで皮膚や体調がよくなる方は今まで数えきれなくらい経験しております。
10年前と比べれば栄養療法に取り組む医師はかなり増えて来ましたが、皮膚科の世界ではまだまだアレルギー、スキンケア、外用剤が中心で、血液検査もアレルギー検査や診断・病勢のためだけです。
血液検査の深読みは、生化学が基本であるため、皮膚科医には馴染みが薄く、難しい内容かもしれませんが、各血液検査項目の意味を理解し、患者さんの体内に生じた代謝異常や病態を十分把握していただきたいと思っています。
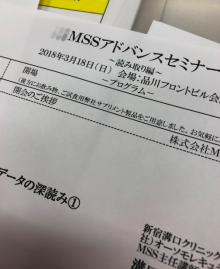
栄養療法の理解を
こんにちは、院長の栗木安弘です。
栄養療法(オーソモレキュラー)を学んでいくと、栄養の重要性をつくづく実感します。
医学的にも、病気と栄養は関わりの深いものですが、
残念ながら、
医学会では診断(疾患)や薬の効果・使い方をばかりが重視され、多くの医師は栄養やサプリメントにはほとんど関心を示しません。
特に学会に参加するとこうした傾向を強く感じます。
また採血結果を見れば多くの方が栄養障害があることは明白ですが、これまた基準値だけでしか判断されないため、ほとんどが見逃されているようです。
糖尿病、高脂血症、アレルギー、精神疾患、自己免疫疾患、免疫低下、動脈硬化、がん、皮膚トラブル、一部の感染症など、ありふれた疾患でもこれといった原因が特定できず、「薬物により症状を抑え、検査異常を無理やり是正」といった対症療法ばかりで、結局薬を一生飲み続けることとなります。
薬も必要でしょうが、長期服用にて栄養障害を生じ、その結果、かゆみや皮膚トラブル、様々な不調や新たな病気の発生、老化促進に繋がります。そういった意味でも栄養療法(オーソモレキュラー)を併用することで体質改善、治癒力アップ、減薬などが期待できます。(医療費削減にも繋がります)
先日のTV番組で娘のアトピーで食事や栄養に関心を持つようになった田舎暮らしの自給自足夫婦が紹介されていました。世間一般には食べ物で身体を良くすることを言われますが、個人的にはもう一歩進んだ栄養療法(オーソモレキュラー)に取り組んでいただくことで、大袈裟かもしれませんが、病気や心身の不調だけでなく、不妊や介護や子供(不登校等)の諸問題など多くの社会問題が解決するような気がしてなりません。
今月、待望のオーソモレキュラー入門が発売されます。この本をきっかけに多くの方のオーソモレキュラーの素晴らしさを理解していただきたと思います。

糖尿病は増えている。
こんにちは、院長の栗木安弘です。
糖尿病及び予備軍は年々増えているようです。
勤務医の時は、糖尿病や透析患者さんがとても多い病院だったので、必然的に合併症の患者(特に糖尿病性潰瘍)ばかり診ていたことが多かったようです。
その中には、血糖コントロールは良好でも、
足の傷がなかなか治らない
再発を繰り返す
頑固なかゆみや湿疹などの皮膚のトラブル
という方も多く経験しました。
当時は処置のやり方や予防(フットケア)が不十分という理由だったかもしれませんが、栄養療法を勉強してから、こうした問題は全て栄養の問題であることが分かりました。
糖尿病というのは糖代謝異常ですが、その背景にはタンパク質・脂質・ビタミン・ミネラル代謝も関わり、互いに歯車のよう代謝が進んでいきます。そのためいくら血糖値だけを無理やり下げても、栄養代謝異常が続く限り、様々な合併症が出現します。
血糖値やHbA1cばかりを注目して対応するのではなく、
なぜ血糖が上がるのか?
どうして血糖が下がらないのか、安定しないのか?
糖を取り込む・インスリン分泌の生化学的な機序
を十分理解して食事(現行のカロリーではなく)や十分なタンパク質・ビタミン・ミネラルの補給、抗酸化対策をしなければ、これからも糖尿病及び合併症は増え続けることでしょう。

皮膚外科
こんにちは、院長の栗木安弘です。
皮膚科の手術と言えば、
傷をきれいに縫合したり、皮膚のできものを切除、植皮などがメインとなります。
外科に比べて短時間で終わりますし、面倒な術後管理もあまりなく、トラブルは少ないようです。
こうした理由から医学部を卒業して、外科的なことができる皮膚科を選択しましたが、
世の中そんなに甘くなく、大学病院時代は、重症患者さんや難しい手術患者さんが入院され、長時間の手術、予想もしない術中あるいは術後トラブルもいくつかありました。
また医局というピラミッド組織であるため、
納得いかない治療方針であっても、やむなく手術をしていたこともありました。
その後、勤務医時代はある程度好きなようなに手術をしておりましたが、
今考えれば栄養状態がよろしくない患者さんは、感染症を併発したり、縫合不全など術後経過もよくありませんでした。
手術の技術を磨くこと、手技を追究すること必要ですが、
栄養療法を知ると、手術がうまくいくための患者さんの栄養状態の把握や対策も同時に必要であると強く感じます。
風邪と栄養
こんにちは、院長の栗木安弘です。
インフルエンザが流行っているようです。私自身、栄養療法を始めてから実感した一つは、風邪をあまりひかなくなったことです。(というか代わりがいないので風邪引けない)
病院勤務時代は、大体3~4か月に一度は疲れがたまった影響で元々ある扁桃腺腫大が悪化し、耳鼻科にお世話になっていましたが、ここ数年はこうした症状は少なくなっています。
仮に発症しても栄養療法と漢方薬で1~2日で回復しますし、インフルエンザもここ5~6年は予防接種はしていませんが発症しておりません。
栄養療法を行っている患者さんも、皮膚の症状はよくならなくても、風邪を引かなくなったという方が多いようです。
予防接種、殺菌、うがいや手洗い、マスク等も必要でしょうが、
タンパク質、ビタミンA・C・D、亜鉛、鉄、オリーブ葉、腸内環境改善などで、 自身の免疫力を上げることも重要な対策となります。
いつも思うのは、病気に対して、薬(塗り薬)、処置、予防接種、体操?など外から人工的なもので何かを施す発想ばかりがTV番組等で注目されていますが、食事や栄養で病気を発症しやすい体質自体を変えていく対策や予防が重要かと思われます。
しもやけと栄養
こんにちは、院長の栗木安弘です。
この時期はしもやけの患者さんがよく来られます。
しもやけは気温4~5℃、日内気温差が10℃以上になると発症しやすく、通常晩秋から冬に発症します。家族内発症が多いことから遺伝的素因も関与しますが、寒冷暴露による血流低下とその回復能力低下が直接の発症原因と考えられています。つまり寒い時期の急激な温度変化に血管がうまく適応できず局所の血行障害が生じるためにおこります。
特に子供はこの温度差による血管の適応能力が未熟なためによく起こります。
栄養学的には虚血~再灌流と言って温度差による血管の急激な収縮・拡張が活性酸素を発生し炎症を起こすことが原因とされ、活性酸素の除去の代表であるビタミンEがよく勧められます。また鉄不足の方も冷え性やしもやけが起こりやすくなります。
治療は保温とビタミンEや漢方薬や血管拡張剤(保険適応外)の内服、ヘパリン類似物資の外用やかゆみや炎症が強い場合にはステロイド外用とされています。しかしビタミンEは保険薬は合成であるため効果は期待できず、子供に関しては漢方薬や血管拡張剤は飲めないため、結局は表面だけの対応となります。しもやけの発症機序から考えれば本来は栄養アプローチが有効だと思われます。
皮膚科での栄養療法
こんにちは、院長の栗木安弘です。
栄養療法も全国的に広がっており、実践している医科歯科機関はたくさんあります。
皮膚科でも栄養療法は行われていますが、他の科に比べればそれほど多くありません。
通常皮膚科というのは、診療単価が他の科に比べて安いので、
患者さんが大勢受診していただくか、レーザーや美容などの自費診療を取り入れなければ、経営的に厳しくなります。
患者数の多いクリニックは限られた時間内で診るのは難しく、
処置や美容関係は看護師がメイン、アルバイトを含めた複数の医師による一人数分の診察にならざるを得ないクリニックもあります。
栄養療法が皮膚科で浸透しない理由の一つは、
忙しい状況で、診察以外に血液検査やサプリメントの説明などで時間をとられることが多く、また皮膚科以外の勉強(栄養代謝等)をしなければならない煩わしさもあります。
実際、クリニックでは難治性のアトピー患者さんは診察や血液検査やサプリメントの説明に30分~1時間ほどかかる方もおられます。
皮膚科は待ち時間が長く診察が短いため、 患者さんの多くは皮膚科に対して
「もっと皮膚をきちんと診てほしい」
「病気の詳しい原因や説明を受けたい」
「根本的に治したい」
といった不満の声をよく聞きます。
またインターネット上でもこうした書き込みやアンケート結果にも反映されています。
https://www.kingdom.or.jp/nanchie/html/09/02_04.html
新患者アンケート
こうした不満を解決するには表面ばかりの対症療法だけでなく、やはり体の内側の栄養対策も皮膚科医には必要とされます。