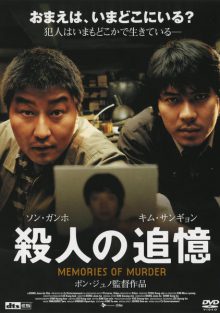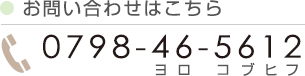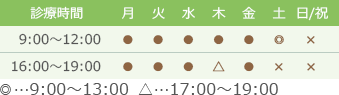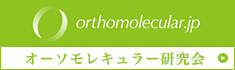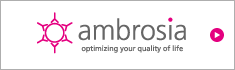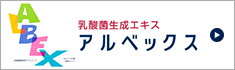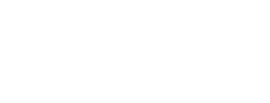皮膚の機能回復
こんにちは、院長の栗木安弘です。
先週の土曜はアトピー性皮膚炎の講演会に出席しました。
栄養セミナーばかりでなく、たまにはこうした皮膚の講演会も勉強になります。
今回は、汗と保湿剤の話でした。
保湿をすることで発汗(基礎発汗)が促され、乾燥肌やアトピー性皮膚炎の改善が期待できるという内容で、やはり本来の皮膚機能を取り戻すことが皮膚の改善につながるというわけでした。逆にステロイド外用剤は発汗の低下を招くため、漫然と長期間使用しないことも述べられていました。
ぬり薬に限らず、薬というのは目的の症状や検査異常を抑えます。
しかし一方で長期間の使用により、体(皮膚)の本来の機能を抑えてしまいます。
保湿もいいかもしれませんが、個人的には体の内側から十分な栄養を与えることが本当の意味での皮膚の機能回復につながります。ただ講演会で紹介された症例も良くなるまで数ヶ月かかっており、皮膚の回復にはやはり時間がかかります。
予防と栄養
こんにちは、院長の栗木安弘です。
がんは2人に1人が発症(発症率50%)する時代ですが、
栄養療法を実践するとがん発症率は5%と言われています。
栄養療法は、がんに限らず、認知症、アレルギー、動脈硬化、アンチエイジングなど様々な疾患の治療だけなく、予防効果も期待ができます。
健康診断で早期発見早期治療が謳われていますが、長い目で見れば、病気を予防することの方が賢明な対策です。
体の仕組みや病気の成り立ちと栄養の関係を理解して対処するだけで、病気の予防が可能となれば、病人も薬も減って、医療費も削減できます。ただこうした情報は、残念ながら医療機関や専門の医師からはあまり積極的には発信されないのが現状です。
サプリメントの理解
こんにちは、院長の栗木安弘です。
最近セミナー等でサプリメントについていろいろ教えていただきます。
サプリメントは、
違法な医薬品成分が含まれていたり、
表示している量が入っていなかったり、
原材料が粗悪、配合量が少ない、
胃や腸で解けずに、便からそのまま出て行ったり、
など、効果もなく法令違反の商品が少なくありません。
また海外から安いサプリメントを購入しておられる方もいますが、日本では違法の成分や医薬品成分が含まれていたりします。つまりサプリメントの世界は一応法律はあっても、何でもありのような状態と思われます。
こうした状況から厚生労働省でも注意喚起がなされています。
医薬品等の個人輸入について
医師のほとんどはサプリメントに否定的ですが、栄養療法で使われるサプリメントは市場に出回っている商品とは全く別物であり、子供から大人、妊婦さんにも安全に長期間使用することが可能で、血液検査で栄養状態を評価できる日本製のサプリメントとなります。
マチネの終わりに
こんにちは、院長の栗木安弘です。
この映画は好みの分かれるところですが、個人的には、今年の日本映画で一番よかった作品です。最初はベタな恋愛映画と思っていましたが、深いテーマのある大人の切ないラブストーリーでした。主人公がクラッシックギターの奏者なので全編にギターサウンドが使用されていて、各シーンととてもマッチしていました。
『三度目の殺人』『SCOOP』『容疑者Xの献身』など福山雅治さん主演の日本映画は意外とハズレが少ないと思いました。
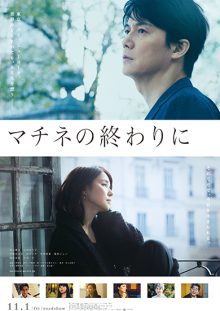
貧血と脂肪肝
こんにちは、院長の栗木安弘です。
病気全体におけるこの2つの疾患が占める割合は非常に大きいですが、
血液検査では正しく診断されていないことがほとんどです。
重症例は容易に診断できますが、
いわゆる隠れ貧血、隠れ脂肪肝が見逃されているケースが多くあります。
血液検査は、脱水、炎症、軽度溶血、栄養障害などの影響で正しい結果が出ません。
このことは多くの医師は理解していません。
ちなみに巨漢のマツコデラックスさんも血液検査は正常ということです。
https://ameblo.jp/healthy-diet-asuka/entry-12258203294.html
こうした影響が栄養療法で取り除かれていくと、見えなかった異常が現れてくることがよくあります。その代表的な疾患が隠れ貧血や隠れ脂肪肝です。
両者に共通しているのは鉄であり、前者は単に鉄不足、後者は鉄代謝異常となり、合併している場合もあるため、その評価はより複雑になります。
両者とも最終的には末梢組織である皮膚が鉄欠乏となり、皮膚のかゆみ、ぶつぶつした湿疹、ニキビ、かぶれ、爪の異常を訴えますが、当然ヘム鉄補給だけでは改善しないこともあります。
子供と栄養
こんにちは、院長の栗木安弘です。
アトピー性皮膚炎、乾燥肌、かゆみ、を訴えて受診されるお子さんは大勢います。
小児科や皮膚科ではお決まりの、
ステロイド外用剤と保湿剤(ほぼヒルドイド)が処方されていて、
ひどくなればステロイド外用、保湿の継続が指導されています。
栄養療法を学ぶと、皮膚に必要なものは、人工的に作られた薬物や保湿剤ではなく栄養であることが理解できます。
子供の成長や発達には大人が思っている以上に栄養が必要となります。
子供は、胎児の時は母親から栄養を奪い、生まれてからは母乳や離乳食では足りないため、自身の体を使ってでまかないます。このため一番犠牲になりやすいのが皮膚や髪の毛や爪や粘膜となります。
栄養が足りなければ、
臓器がうまく作られません。(先天性疾患)
皮膚や粘膜のトラブルも起こします。(湿疹、ニキビ、感染症、喘息、アレルギーなど)
子供には、生まれる前から栄養対策が必要ですが、残念ながら食事だけでは難しいようです。
爪の切り方
こんにちは、院長の栗木安弘です。
最近SNSで爪の正しい切り方が話題になっています。
出来るだけ短く切らないこと
爪の端を残して切る
という深爪をしない切り方は、巻き爪を予防するもので、以前から皮膚科の間では当たり前のように指導されていました。
しかしよく考えば、深爪の方全員が巻き爪になるわけではありませんし、
爪が長いままだと、うっとおしい、割れたり欠けたり、靴下の繊維や黒い汚れが付着することがあリます。そう言った理由で、私自身も結構短く切ることがほとんどですが、巻き爪になったことは一度もありません。
個人的には、巻き爪も栄養障害だと思います。
爪の下の皮膚の弾力性(真皮や脂肪隔壁はコラーゲン)が低下すると足底からの刺激により、爪の周囲の皮膚が盛り上がって、爪直下の骨によって爪が押され、巻いて来ます
採血結果でもタンパク質や鉄不足の方がほとんどです。
ただし深爪同様、栄養障害の方全てが巻き爪になるわけではありません。
そこは医学的には証明の難しい個人差というところがあります。
リアルSF
こんにちは、院長の栗木安弘です。
『アド・アストラ』観てきました。
宇宙を舞台にしたSF映画と言えば『スターウォーズ』みたいに、
ワープ機能でスイスイ移動
でっかい宇宙船内でみんなで楽しい旅行
勧善懲悪、宇宙人いろいろ
という派手でエンターテイメント性が強いようですが、
『アド・アストラ』はリアルSF映画で、暗く重たくスカッとする感じではありません。
前評判は良かったようですが、個人的には同じリアルSFなら『オデッセイ』『ゼロ・グラビティ』『インター・ステラー』の方が良かったです。
それより、登場人物は太陽に当たらない閉鎖空間での生活をしていましたので、ビタミンD不足にならないか心配でした。当然宇宙船にはサプリメントは積んでいるとは思いますが、長年栄養療法を学んでいますと、こうしたことも気になります。

ニキビが治らない
こんにちは、院長の栗木安弘です。
時々ニキビの治療をしても良くならない方が受診されます。
そういった場合には、食事指導や栄養療法の説明をさせていただきます。
ニキビ専門家に言わせれば、
「エビデンスが乏しいので食事や栄養はあまり関係ない」
「肉や脂っこいものを控える」
ということですが、普通に考えれば、体は食べたもので作られますので、皮膚の再生や修復する材料がなければ、あれこれ塗ったり、美容処置を行っても良くなりません。仮に良くなっても再発を繰り返します。
ニキビに必要な栄養は、まずタンパク質と鉄(特に女性)です。
そして皮疹の性状や分布を診て、
皮脂の多い方は、ビタミンB群やビタミンCやビタミンE
毛穴のつまりが目立つ方は、ビタミンAや亜鉛
をお勧めしており、当然この辺りは医師として血液検査できちんと確認するようにします。
アダパレン、過酸化ベンゾイルの刺激やかぶれ
ビタミン剤はおまけ(ビタミンを正しく理解されずに処方)
抗生剤の長期使用による耐性や腸内環境悪化
漢方薬による肝障害
美容処置のトラブル
などのニキビ治療にはいくつかの課題や問題があります。
ニキビの安全な治療と予防には、妊婦さんや子供など誰にでも応用できる栄養療法がお勧めとなります。
韓国映画ファン
こんにちは、院長の栗木安弘です。
日本と韓国は仲が悪いようですが、韓国映画は個人的には大好きです。
見たい作品は、わざわざ上映している映画館に足を運んだり(主に心斎橋シネマート)、見逃した作品はレンタルやブレーレイを購入して鑑賞しています。韓国映画は、テーマの重い作品が多く、観終わったあと疲れますし、また犯罪ものやヤクザものは、暴力や痛いグロいリアルな描写が多くて、トラウマになる作品もあります。それでも日本映画よりもレベルは高いと個人的には思っています。
印象に残る作品はいろいろありますが、大きく分けますと、
●良作ですが、二度と観たくない作品:血祭りトラウマ級ですので勇気のある方はぜひ。
「哀しき野獣」「チェイサー」「新しき世界」「シュリ」「ブラザーフッド」「悪女」
●何回も観たい作品:ハラハラドキドキ、泣ける。
「殺人の追憶」「グエムル:漢江の怪物」「新感染」「ザ・タワー」「テロ・ライブ」
「私の中の頭の消しゴム」「監視者たち」
がオススメです。